
フコク生命とJAの違い~ 3歳、6歳、12歳、15歳、18歳、22歳は両社同じです。フコク生命に成人式分があるので1回多くなっています。
今回取り上げた中で、JAにじ、JAえがおの2プランのみ元本割れとなっています。これは、保険や育英年金がセットされているためです。

2-3-2「小学校入学時から受け取るタイプ」の比較
JPかんぽ生命「小・中・高+大学入学時」の学資金準備コースと日本生命保険「ニッセイ学資保険祝い金あり」の2種類が該当します。
比較の条件を記載します。
JPかんぽ生命 契約者30歳(男) 被保険者0歳 保険期間18歳 保険料払込期間18歳
ニッセイ学資保険 契約者30歳(男) 被保険者0歳 保険期間22年 保険料払込期間18歳
| 月支払額 | 受取保険 | 6歳 | 12歳 | 15歳 | 18歳 | 19歳 | 20歳 | 21歳 | 22歳 | 満期返戻率 | 年利 | |
| 単位 | 円 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | % | % |
| JPかんぽ | 11,800 | 260 | 10 | 20 | 30 | 200 | 無 | 無 | 無 | 無 | 102.0 | 0.24 |
| ニッセイ | 10.278 | 216 | 12 | 12 | 12 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 103.1 | 0.32 |
2社のプランの違いは、大学入学後に受け取れるか否か、という点です。早めに祝い金を受け取るとどうしても年利換算では低い値となりますね。
2-2-3「中学校入学時から受け取るタイプ」の比較
対象とした5社の中では、ソニー生命学資保険スクエアⅠ型のみです。他の商品同様、内容を見ておきましょう。
契約者30歳(男) 被保険者0歳 保険期間22年 保険料払込期間17歳
| 月支払額 | 受取保険 | 12 | 15 | 17 | 22 | 満期返戻率 | 年利 | |
| 単位 | 円 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | % | % |
| ソニー生命 | 8,400 | 182 | 21 | 21 | 70 | 70 | 106.2 | 0.59 |
2-3-4 「大学入学以降に1~2回受け取るタイプ」の比較
フコク生命みらいのつばさジャンプ型、ソニー生命学資保険スクエアⅢ型、JPかんぽ生命の3プランが該当します。
| 月支払額 | 受取保険 | 18歳 | 22歳 | 満期返戻率 | 年利 | |
| 単位 | 円 | 万円 | 万円 | 万円 | % | % |
| フコク生命 | 8,897 | 200 | 100 | 100 | 110.1 | 0.83 |
| ソニー生命 | 8,832 | 200 | 100 | 100 | 110.4 | 0.85 |
| JPかんぽ生命 | 8,920 | 200 | 200 | 無 | 103.8 | 0.4 |
JPかんぽの満期返戻率および年利の低さが目立ちますが、これは保険が特約でついていること、満期が18歳と早いことが原因です。
ともあれ、このタイプが最も有利な運用となります。今回、JPかんぽ生命は貯蓄性重視の商品に切り替えて来たようですが、補償性重視という側面も残しているようで思い切りが少し悪いかな、という気もします。
ただ、満期が22歳というのは、実際に必要な時期に資金を使えない可能性があるのではないか、という気がします。確かに大学を卒業し社会人になる時は意外にお金がかかります。
まだ子供に収入が無ければ、親からの持ち出しとなるでしょう。私もそうでした。
引っ越し代、初任給が出るまでの生活費、悲鳴を上げたくなるほど色々とかかりました。でも、そのために積み立てるのは、「学資保険」という本来の目的とは違うような気がするのですが、どうでしょう。
2-3-5 「大学入学以降3回以上で受け取るタイプ」の比較
ソニー生命学資保険スクエアⅡ型、JPかんぽ生命大学入学時+在学中の学資金準備、日本生命保険ニッセイ学資保険祝い金なし、JAステップ が該当します。
ソニー生命 契約者30歳(男) 被保険者0歳 保険期間 22歳 払込期間 17歳
JPかんぽ生命 契約者30歳(男) 被保険者0歳 保険期間 21歳 払込期間 18歳
日本生命 契約者30歳(男) 被保険者0歳 保険期間 21歳 払込期間 18歳
JAこども共済 契約者30歳(男) 被保険者0歳 保険期間 22歳 払込期間 17歳
| 月支払額 | 受取保険 | 18歳 | 19歳 | 20歳 | 21歳 | 22歳 | 満期返戻率 | 年利 | |
| 単位 | 円 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | % | % |
| ソニー生命 | 8,832 | 200 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 110.4 | 0.85 |
| JPかんぽ生命 | 8,740 | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | 無 | 105.9 | 0.54 |
| 日本生命 | 9,625 | 210 | 70 | 35 | 35 | 35 | 35 | 106.9 | 0.65 |
| JAこども共済 | 9,044 | 200 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 108.4 | 0.69 |

3 各商品の人気の理由を探る。
3-1 フコク生命「みらいのつばさ」
3-1-1 商品内容の単純化、セールスポイントの明確化の勝利
第1位になった要因は、商品内容の単純化と高い満期返戻率をセールスポイントにしたことあります。
他社が顧客のニーズに応じるべく払込期間や保険満期をさまざまに設定し、結果的に複雑な商品内容になるなかで、プランはステップ型、ジャンプ型2種類のみ、払込期間と保険満期は1種類のみという単純な商品内容。
利差配当金もなし、そのかわり満期返戻率は高率になっています、という点に絞ったセールスポイント。かつて金融商品を販売する営業の立場にあったものとしては、非常に売りやすい商品だと思います。
保険を契約する立場からしても、考える余地が少ないのは、かえって決断までの時間が少なくて済むのかもしれません。
確かに「払込期間をこうすれば、満期返戻率はこうなります。この場合にはこう」、といろいろなシミュレーションをしていくなかで、自分に最適な条件を選択できるということもあるのでしょうが、反面そのような作業を面倒と感じる人もいるのではないでしょうか。
アンケートに回答した加入者の感想も、「高い満期返戻率」と「わかりやすいプラン内容」の二つに集約されています。
ただ、学資保険の本来の目的からすると、大学入学時と学生時代が最もお金が必要な時期に資金が使えないというのは、やはりネックになると思います。
保険というのは長期の商品ですので、契約する時点では満期返戻率にばかり注目してしまい、どのような受け取りのスケジュールとなっているのかは二の次になっているのかもしれない、とも感じます。
また、今回上位に入った保険の中では唯一「利差配当制度」がない商品でしたが、現状では配当が発生するような経済状況ではないと私も思いますので、販売上のネックとはならなかったのでしょう。契約者の方もそのように判断されているのではないでしょうか。
3-2 ソニー生命学資保険スクエア(Ⅰ型~Ⅲ型)
3-2-1 ライフプランナーによるコンサルテイング営業の勝利
今回ベスト5に入った保険会社の中では新興勢力と言っていいソニー生命。当初は外資系との合弁でした。
完全にソニーの子会社となったのは1996年、2004年にソニーフィナンシャルホールデイングスの傘下に入りました。国内の老舗の保険会社で新規の契約契約が伸び悩む中、ライフプランナーによるコンサルテイング営業に力を入れ契約数を伸ばしています。
今回はフコク生命の後塵を拝することになりましたが、様々な顧客ニーズを取り込みべくプランや払込期間、保険満期について複数の選択肢を設けています。
フコク生命に比べると商品内容が複雑化しているわけですが、ライフプランナーによるコンサルテイング営業により商品内容の周知を図るというやり方で、契約数を伸ばしています。
加入者の感想をみても、フコク生命と同様「高い満期返戻率」と並んで、「プランナーの説明がわかりやすかった」と答えた方が多かったのも肯けるところです。
満期返戻率は月払いで比較した場合、フコク生命と同水準の設定となっています。さらに高利回りをうたうスクエアⅢ型は、支払期間を10年に設定でき、月々の支払いに余裕がある方にはフコク生命よりも高い満期返戻率を示現できます。
今後金融情勢が好転した場合、5年ごとに利差配当が付く可能性があるので、フコク生命よりも有利な運用ができるかもしれません。(この20年の低金利政策と、それに輪をかけるようなマイナス金利政策などを考えると、あまり期待はできませんが)
3-3 JPかんぽ生命
3-3-1 かつての学資保険の王者 過去の栄光から脱却できるか?
かつて業界トップに君臨していた企業が、古いやり方に固執するあまり変化について行けず脱落していく、どのような業界でもよくある話です。
過去の栄光や実績を捨てて新たな商機をつかみ、人気を獲得するというのは、やらねばならないと理解はしていても実際にはなかなか難しいものです。
JPかんぽ生命は、「小・中・高+大学入学時コース」「大学4年間コース」「大学入学時コース」の3コースを投入。従来の保障型から貯蓄重視の学資保険へ転向を図りました。
一方で希望すれば医療保障も付けられるという「かんぽ」本来の商品も残っています。
ただ今後、貯蓄重視に特化していくのか、従来どおり補償型を主力にするのか、方針を徹底しないと伸び悩むことになるのではないか、という危惧も残ります。
満期返戻率は、保険期間や払込期間などを同条件に引き直した場合、②小学校入学時から受け取るタイプ、④大学入学以降に1~2回受け取るタイプ、⑤大学入学以降3回以上で受け取るタイプの3タイプ全てで最低の満期返戻率となっています。
加入者の感想は、「郵便局だから安心」と「勧誘されたから」がほとんどを占めており、民営化したとは言いながら郵便局というネームバリューと、昔ながらの「訪問勧誘」という手法が、まだまだ力を持っているんだということを実感させられる結果だと思いました。
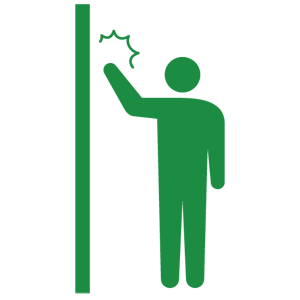
3-4 日本生命保険相互会社・ニッセイ学資保険(祝い金無,有)
3-4-1 やはり国内生命保険会社のガリバー的トップの貫録
やはり、日本最大手の生命保険会社の貫録だと思いました。加入者の感想は「満期返戻率が良い」というものがほとんど。
しかし上記の表でもわかるとおり、満期返戻率はフコク生命はソニー損保に比べダントツに良いという訳ではないのですが。やはり日本生命に対する信頼感なのかな、とも思います。
ただ、2014年に保険料を改定する前はもっと満期返戻率が高かったとのことす。生保業界のリーデイングカンパニーなるが故に、極端に高い満期返戻率は設定しづらいのかもしれません。
私も以前、日本生命の「こども保険」に加入していましたが、補償重視の内容であまり使い勝手はよくありませんでした。
大学入学と在学中に学資金を受け取れるという現在の保険は、現実的で良い内容だと思います。
3-5 JAこども共済学資金型ステップ
3-5-1 補償性に特化するのか、貯蓄性に行くのか、方向性が良くつかめません。
今回ランクインした保険の中で、唯一満期返戻率がマイナスになったプランがこの「JAこども共済学資金型ステップ」です。
得意な医療保険では手厚い保障がセールスポイントになっているようですが、一方で満期返戻率に特化した「ステップ型」という商品も投入されています。
中途半端、徹底していないと感じるのですがいかがでしょうか?
JA共済は昔からかなりの人気と実績があるので、JPかんぽ同様なかなか過去の栄光から脱するのは難しいのかな、とも思います。
「貯蓄型にも保障型にもなれる万能型」という評価もあるようですが、「何でもできる」というのは結局「どっちつかず」という点にも通じるので、今後どのような販売方針で臨むのか、注視していきたいと思います。
ただ、JA共済は販売チャネルに独自のものを持っています。加入者の回答も「勧められたから」というものが多いのも特徴で、単純に商品内容だけでは計り知れないものがあるのかもしれません。
3-6 もし、今自分が加入するとしたら
自分であれば、上記5社の中から選択するとすれば、「⑤大学入学以降3回以上で受け取るタイプ」から選ぶと思います。
私の娘は今年大学を卒業しましたが、高校入学までは特に学資金や祝い金は不要であった、というのが実感です。
やはり大学の入学時と、その後4年間の仕送りが大変でした。この間の学資金の補助とするため、というのが一番現実的ではないかと思います。
保険会社については、もちろん返戻率も重視しますが、商品説明を丁寧に行ってくれるのか、アフターサービスはどうなのか、という点にも考慮して選びたいと思います。
利差配当については現状では期待できないので、それほど重視はしないと思います。
4「低解約返戻金型保険」について
最初にご紹介したアンケート結果で、「300サンプルのうちの3分の2が学資保険以外に加入しているという、ちょっと意外な結果がでています。」と申し上げました。
300サンプルのうちの200というのは尋常な数字ではないので、最後に少し触れておきます。
4-1 人気急上昇中の「低解約返戻金保険」
今回は「学資保険」の人気商品を中心に進めてきました。ここまででもかなり長くなっているので、詳しくは触れませんが現在、「低解約金返戻保険」の人気が急上昇しているそうです。おそらく、200サンプルのかなりの部分がこの保険ではないかと予想しています。
オリックス生命保険の「RISE」という保険を見てみましょう

保険の内容としては、
① 死亡・高度障害に対する保障が一生涯続く。
② 保険料払込期間(低解約払戻期間)中の解約払戻金を抑制することにより、手頃な保険料を実現。
③ 解約払戻金があるため、一生涯の死亡保障に加え、長期的な貯蓄機能も備えている。
④ 重い障害になった時に、保険金を前倒しで受け取れる。
⑤ 事故により約款所定の身体障害の状態になった場合、以後の保険料の払込みが免除され保障が継続。
⑥ 余命6か月と診断された場合、死亡保険金額の全部または一部に相当する金額が生存中にさはらわれる。
(「オリックス生命保険」公式HPより)
上記を見ると、特に学資保険として加入しているという訳でもないのかな、とも思います。景気の良いころであれば、学資保険とこの保険両方に加入するという選択もあったかもしれません。
家計の支出を増やすことが難しい現状、出来るだけ汎用性の高い学資保険が人気を集めるという傾向が今後も続いていくかもしれないと思わせる結果でした。今後、この流れが続いていくのかどうか、注視していきたいと思います。
以上、お読みいただいてありがとうございます。